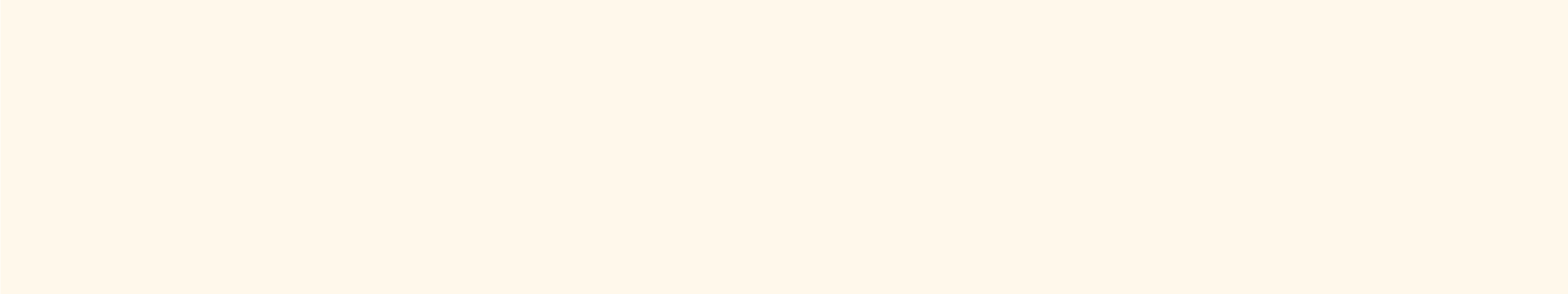Q1.「常時雇用する労働者」が101人以上であれば女性活躍推進法の取組が義務づけられていますが、「常時雇用する労働者」にはどのような従業員が含まれますか。海外事務所の駐在員や、学生のアルバイトも含まれますか。
A1.「常時雇用する労働者」とは、正社員、パート・アルバイトなど雇用契約の形態にかかわりなく、次のような人をいいます。
①期間の定めなく雇用されている人。
②期間を定めて雇用されている人であって、
・過去1年以上の期間について引き続き雇用されている人 または
・雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる人。
なお、海外にある支店・出張所等で雇用されている人は、法の適用を受けるかどうかの企業規模の判断においては、「常時雇用する労働者」にはカウントしません。
また、昼間は通学している学生・生徒は、アルバイトとして長く勤務している場合でも、法の適用を受けるかどうかの判断においては、「常時雇用する労働者」にはカウントしません。なお、学生・生徒でも夜間や定時制・通信教育で学ぶ学生の場合は、1年以上雇用されている(またはその見込みである)場合はカウントしてください。
ちなみに、状況把握や情報公表の取組の対象は雇用する労働者すべてが対象となります。つまり、「雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれない者」や「学生アルバイト」なども、状況把握、情報公表の対象とする必要がありますので、ご留意ください。
Q2.管理職に占める女性の割合を算出して公表することが今後義務づけられることになるとのことですが、「管理職」とは具体的にはどの範囲をいいますか。
A2.「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます。
「課長級」とは、次のいずれかに当たる人をいいます。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている人で、その人が長を務める組織に2つ以上の係があること、もしくは、その構成員が 10 人以上(課長本人を含む)であること
②同一事業所において、役職の名称や構成員の人数に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと)
「課長級」かどうかについては、まず①のとおり、役職の名称や係の数、構成員の人数等で形式的に該当するかどうかを判断します。次に、形式的な要件に該当しない場合は、②のとおり、同一事業所において、課長以外であっても呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する(ただし、一番下の職階ではない)かどうかを判断します。
いってみれば課長級とは、職場の一つの組織において業務遂行の方針の決定や部下への業務指示・育成等に責任を持つ立場であり、そうした立場に女性がどれほど配置されているかをはかるという観点で、職場の実情に応じて判断することになります。このため、「営業所では課長だが、本社に異動すれば係長である」という場合は、営業所で課長級の役職についている間は、課長級とカウントして算出します。
Q3.常時雇用する労働者101人以上300人以下の企業に男女の賃金差異の公表が義務づけられるとのことですが、男女の賃金差異はどのように算出したらよいですか。
A3.男女の賃金の差異は、①雇用するすべての労働者(全労働者)、②正規労働者(正社員)、③非正規労働者(パート・アルバイトなど正社員以外の人)の3つの区分について算出し、公表することが求められます。
算出方法は、
・まず、賃金台帳、源泉徴収簿等を基に、3つの区分それぞれについて、男女別に直近の事業年度の賃金総額を計算し、当該事業年度に雇用したそれぞれの区分の労働者数(人数)で割り算して、平均年間賃金を算出します。
・3つの区分それぞれについて、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で割り算して100をかけた数値(パーセント)が、男性の賃金を100としたときの女性の賃金の数値となります。
小数点以下第2位を四捨五入し、小数点第1位まで公表します。
直近の事業年度の実績を、おおむね3か月以内に公表してください(事業年度が毎年4月から翌年3月の企業では、おおむね6月末までに公表します)。
賃金差異の算出について詳しくは、厚生労働省ホームページに解説とQ&Aが掲載されています。
厚生労働省の「男女間賃金差異分析ツール」はExcelで簡易に男女の賃金の差異を算出し、さらに賃金の差異の要因分析や産業平均値との比較が可能で今後の取組のヒントが得られるツールです。ぜひご活用ください。
参考:男女間賃金差異分析ツール(Excel)
Q4.「常時雇用する労働者」が100人以下の企業です。女性活躍推進法の取組は義務づけられていませんが、取組を行うと公共調達等で優遇されるのでしょうか。
A4.女性活躍推進法に基づく認定企業(「えるぼし」認定、「プラチナえるぼし」認定)等は公共調達で有利になります。
また、常時雇用する労働者が100人以下の企業の場合は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行うだけで公共調達の加点の対象となります。詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)について | 内閣府男女共同参画局
さらに、日本政策金融公庫の働き方改革推進支援資金を通常よりも低金利で利用することができる制度もあります。詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご参照ください。
働き方改革推進支援資金|日本政策金融公庫
Q5.女性活躍推進法に基づく取組についてアドバイスがほしいときは、どこに相談したらいいですか。
A5.女性活躍推進法に基づく取組についてのお問い合わせ・相談は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が受け付けています。電話または来庁でご相談ください。
受付時間は平日8時30分~17時15分です。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)一覧
一般事業主行動計画策定等届や「えるぼし」等認定の申請の提出先も、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。郵送または来庁での提出の他、電子申請もご利用になれます。
電子申請ポータルサイト:トップ | e-Gov電子申請
※一般事業主行動計画策定支援ツール、男女間賃金差異分析ツールなどを活用して取り組むときはこちら
女性活躍推進法特集ページ
よくあるご質問をご覧いただいてもなおご不明な点やお悩みがございましたら、
専門家による個別のご支援も可能です。
貴社の状況に寄り添ったご提案をいたしますので、ぜひ専門家派遣をご活用ください。
令和7年度 民間企業における女性活躍促進事業事務局
厚生労働省「男女間賃金差異分析ツール」の作動方法・不具合など技術的な内容に関するお問い合わせ
下記の「お問い合わせフォーム」または「電話」にてお問い合わせください。
(事務局) 電話 03-6206-7072(平日9:00~17:00)
本事業は株式会社タスクールPlusが厚生労働省より委託を受け、事業を運営しております。
当事業に関するお問い合わせもこちらからお願いします。